

|
地球のために… 冷媒センサによる、 冷凍機監視システム。 ●冷媒不足の予知が可能になります。 ●ファジーコントロールで機種を選びません。 ●冷媒充填は、誰でも適正量になります。 ●CPU搭載で、学習機能でさらに精度アップ。 |
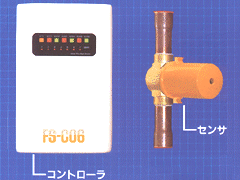 |
|
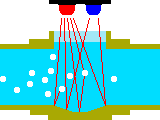
|
||
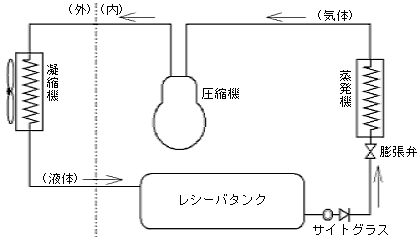
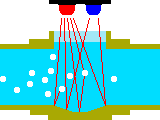 泡の量によって戻る光の量が変化する。 |
|
1.透過式 (光線8本:泡5個) 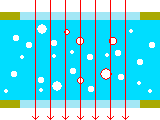 透過式では、直線的な光の動きのみで右図に比べて泡を通過する光の数が少ないので変化も少ない。 |
2.反射式 (光線5本:泡11個) 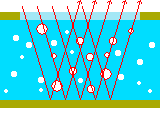 反射式では、進入光が泡を通過した後、同じ光が今度は、戻り方向に向かい再度泡を通過するので光に対する泡の影響が大きい。 |
| 品名 | 型名 | 価格(円) |
|---|---|---|
| センシングシステム制御部 | FS-C06 | 280,000 |
| センシングシステムセンサ部 | FS-P03 | 18,000 |
| サイトグラス3/8 | FS-SG-10 | 4,000 |
| サイトグラス1/2 | FS-SG-12S | 4,000 |
| サイトグラス5/8 | FS-SG-16S | 5,000 |
| サイトグラス3/4 | FS-SG-19S | 6,500 |
| サイトグラス7/8 | FS-SG-22S | 7,000 |
| サイトグラスオーダ | FS-SG-ORG | 9,000 |
| メンテナンスプログラムA | FS-MP06AW | 48,000 |
| メンテナンスプログラムB | FS-MP06B | 100,000 |
| メンテナンスプログラムC | FS-MP06C | 600,000 |
| リモートプログラム | FS-MP06R | 50,000 |
| メンテナンスケーブル | FS-MC-2 | 8,000 |